平成27年4月より、厚生労働省が放課後等デイサービスの支援の質向上を図るため、「放課後等デイサービスガイドライン」が定められました。放課後等デイサービス カリタス翼ではこのガイドラインに基づき、「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」「事業者向け・放課後等デイサービス自己評価表」を公開いたします。
以下のPDFをご覧ください。
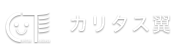
平成27年4月より、厚生労働省が放課後等デイサービスの支援の質向上を図るため、「放課後等デイサービスガイドライン」が定められました。放課後等デイサービス カリタス翼ではこのガイドラインに基づき、「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」「事業者向け・放課後等デイサービス自己評価表」を公開いたします。
以下のPDFをご覧ください。
平成27年4月より、厚生労働省が放課後等デイサービスの支援の質向上を図るため、「放課後等デイサービスガイドライン」が定められました。放課後等デイサービス カリタス翼ではこのガイドラインに基づき、「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」を公開いたします。
以下のPDFをご覧ください。
放課後等デイサービス カリタス翼では毎年、障害あるお子様たちが自然のなかで集団生活を体験することを目的に、夏合宿を行っています。
今年も長野県の高遠青少年自然の家で、ハイキングや野外炊飯などを行います。
夏合宿では、ボランティアの皆さまに一対一でお子様を担当していただいています。毎年多くのボランティアの皆さまが、障害のあるお子様たちのために、熱心に活動して下さっています。
お子様たちにとっても、ボランティアの皆さまと一緒に過ごす夏合宿をとても楽しみにしています。また、ご家族にとっても、つかの間の貴重な休息となっています。
このような活動ができるのも、ボランティアの皆さまのご協力のおかげと感謝しております。今年も是非、皆様のご参加・ご協力をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。
<2016年度 カリタス翼 夏合宿>
・日時:2016年8月10日(水)~8月12日(金) 2泊3日
・場所:国立信州高遠青少年自然の家
・集合場所:公益財団法人 東京カリタスの家
(東京都文京区関口3-15-16 護国寺駅/江戸川橋駅より徒歩10分)
・参加費は無料です。集合場所(東京カリタスの家)までの交通費はご負担ください。
なお合宿に先立ち、プレ合宿(事前説明会)を行います。昨年度の合宿の様子や、障害のあるお子様との関わり方について具体的に説明をしますので、必ずご参加ください。
<プレ合宿(事前説明会)>
・日時:7月9日(土)10時~17時
・場所:公益財団法人 東京カリタスの家
(東京都文京区関口3-15-16 護国寺駅/江戸川橋駅より徒歩10分)
・当日の昼食はこちらで準備します。筆記用具をご持参ください。
ボランティアへのお申し込みは、以下の申し込みフォームにアクセスし、必要事項を入力して送信ボタンを押してください
申し込みフォーム
※PCやスマートフォン以外の携帯電話は下記のフォームから申し込みができないので、メールにて参加の有無をお知らせください。
